
これは!?珍しい金箔入りの梅干しか?
いやいや、そうではない。塩と砂糖で漬けた我が家特製の単なる梅干しである。2年前に漬けた、令和元年ものの。
豊作の年、不作の年
毎年6月頃、梅をたくさんいただける。しかし、一般家庭の管理する梅の木なので、たまに不作の年もある。豊作の年もしかり。
令和元年、つまり2年前に、けっこう豊作だった我が家の、というか夫の実家の梅。梅シロップと梅干しにした。
梅干し1瓶、梅シロップ2瓶の割合で漬ける。元々は梅干しは塩のみで漬けていたが、塩がきついとあまり食べられないので、半分砂糖で漬けてみた。それでも大丈夫だったし、味が少しまろやかになって食べやすいので、令和元年も砂糖と塩を半分ずつの割合で漬けた。
梅干しはシロップよりもすぐできる。そうだ、確か干さないで作ったのがこの年だったか。干さなくても干してからまた汁に戻しても、同じ事だと思った。多少乾いている方が美味しいのだが、乾きすぎて塩が表面に出てきているような古い梅干しは好きじゃない。
ともかく、出来上がった梅干しを、比較的小さい小瓶に移して保存していた。ジャムの空き瓶などを利用していた。
令和2年は梅が不作だった。梅干しは余っているし、いただいた梅は全てシロップにした。
令和3年は、一粒が大きい梅が収穫された。キロ数で言うとけっこういただけたのだが、個数が少ないので、今回も梅干しは作らず、シロップだけにした。何しろ、梅干しがまだ余っているし。
汁が下に溜まっていたので
梅干しは、食べようと思えば食べるのに、何となく食べずに残ってしまう事が多い。料理に使ってもいいし、お弁当に入れれば減るのだが、何となく余り気味になる。
それでも、ようやくあと2瓶で無くなる。昨日、今まで食していた瓶に最後の一個が残っているのを見て、もう1瓶出してきた。
出してきたら、下の方に汁が溜まって、上の方は乾いている。それで、瓶の蓋を閉めたまま、がしゃがしゃと振れば全体に汁が混ざると思った。
ここが運の尽きだったのだが、その時の私には分かりっこない。
瓶を見て、白っぽいというか、金色っぽいものが見えたが、塩の塊だと思った。
蓋が!
そして、夕べの食卓にその梅干しを出した。
蓋を開け、中を覗いたら・・・冒頭の写真である。
塩の塊ではないようだ。
長男が、
「あっ!これ!」
と言った。彼を見ると、指を差している。その差しているものは・・・
瓶の蓋だった。やあ!なんだこれは!
最初は、黒い物が付いているのかと思った。しかし、触ってみるとそうではない。剥けているというのか、腐食して剥がれているのだ。

梅干しは酸性だ。酸は金属を溶かすかもしれない。だが、今までだってずっと瓶に入れてきたし、ほら、今まで食べていた梅干しの瓶は同じ瓶なのに、蓋は綺麗なままだ。
それにしても、1年以上経つ事があっても、2年以上置いておいた事はなかったのかもしれない。保存瓶の蓋はガラスやプラスティックだが、こういう瓶は鉄製だから。ちなみにこの瓶は、元々きゅうりのピクルスが入ってたものである。
しかし、金箔入りのものを飲んだり食べたりする事もあるのだし、この梅干しをこのまま食べても大丈夫なのでは?
と思ったが、これが純粋な鉄かどうか分からないので、このまま食べるのはよしておこうと思う。
一粒洗ってみた。洗えば金属は取れるし、食べるとむしろ塩っ気が減って美味しい。
もうこれは、毎日食べる分だけ洗って、みんなでたくさん食べるしかない。
それにしても、瓶を振ったりしなければ良かったのに。まずは開けて確認してから・・・って、まさか蓋が腐食しているとは思わないのだから、無理だよな。
もう1瓶残っている
そして、恐ろしい事に、もう1瓶残っている。
それを今朝、確認してみた。これも上の方が乾いているが・・・開けてみようと思ったら、開かない。道具を使えば開くだろうが、相当固い。

そうか、昨日は瓶の蓋が、振っている時にも開いてしまったくらい緩かったな。そのせいなのだろうか。もしくは、今日の瓶は小さいから中身も少ない。酸の量の違いとか?
で、この固くしまった瓶の蓋の内側は、下から見る限り腐食してはいない。良かった。
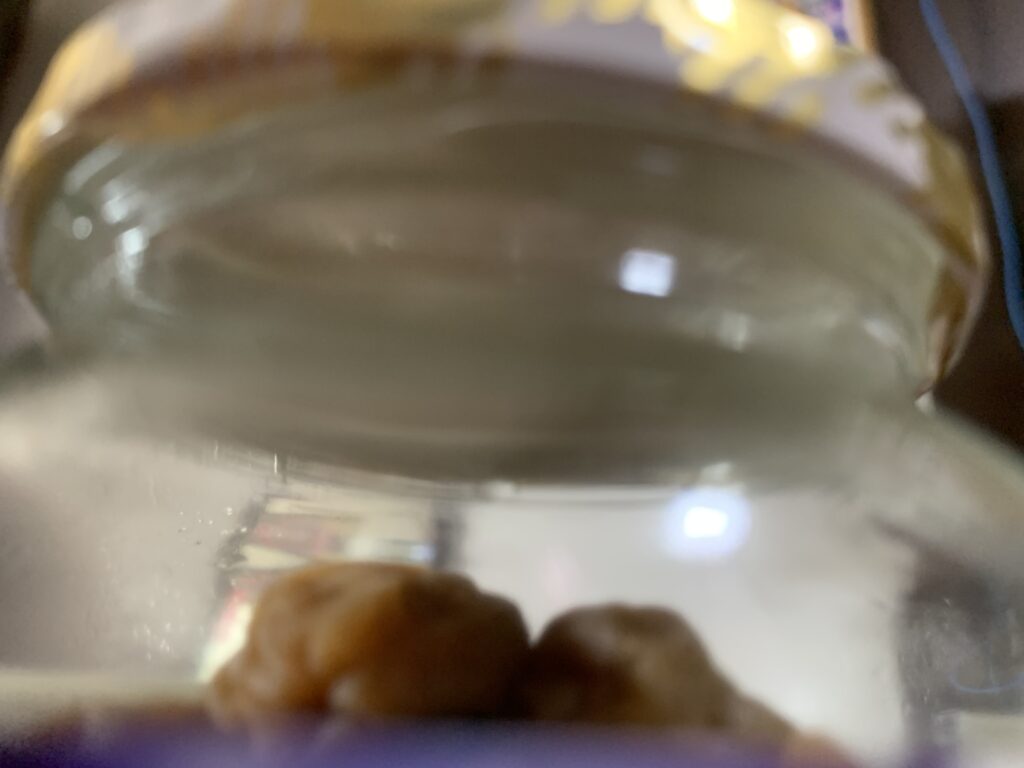
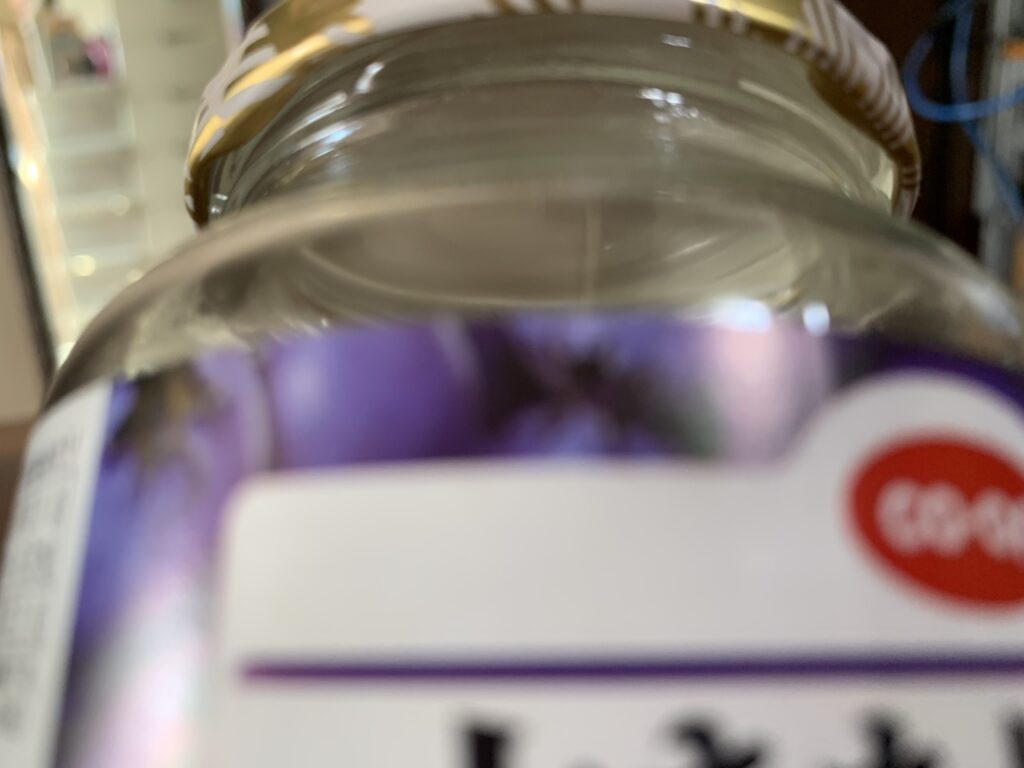
だが、ここで一つ疑問が。
もしかしたら、昨日の大きい瓶だって、この時点では大丈夫だったのに、振って刺激したことで、初めて剥がれたという事もあるのではないか。
それで、私は今日、恐る恐る小さい瓶の方も振ってみた。何しろ、汁が下に溜まっているしね。
振ったが、今のところ蓋の内側は白いままのようだ。良かった。
というわけで、梅干しを長期保存する場合は、金属の腐食にご注意を。だが、2年以上保存しない方が無難である。早く食べてしまうか、余ったら梅びしおとか、かつお梅とか練り梅とか、何かに加工したりしてみるとよいと思う。